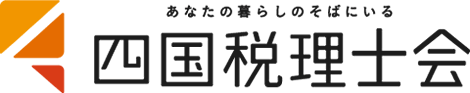税理士制度の沿革
| 『税務代理業の発生』 | |
|---|---|
| 明治29年 (1896年) |
税務代理業務が生まれたのは、遠く日露戦争の当時にさかのぼります。日清戦争後の財政負担増を賄うため、明治29年に営業税法が制定されました。その後、日露戦争の勃発に伴う相次ぐ増税で税務相談等を依頼する納税者が急増し、税務相談等を独立の業とする職業が生まれました。 |
| 『税務代理業の発生』 | |
| 明治45年 (1912年) |
税務代理業者の中には納税者の依頼に十分こたえることのできない不適格者も出てきましたので、その取り締まりを目的として、明治45年5月16日に大阪府令で「税務代弁者取締規則」が制定されました。その所管は警察官署でした。 |
| 『税務代弁者取締規則の制定』 | |
| 昭和17年 (1942年) |
昭和2年に計理士法が制定され、その後第二次世界大戦時下の財政重要度が高まるにつれ、税務行政の適正な運営を図る見地から、昭和17年2月23日「税務代理士法」が制定されました。弁護士、計理士、判任官以上で3年以上国税の事務に従事した者等が有資格者で、大蔵大臣の許可を受け、税務書類の作成、税務代理、税務相談を業としました。わが国における税理士制度は、この税務代理士法により初めて確立されたということができます。 |
| 『税理士法の制定』 | |
| 昭和26年 (1951年) |
戦後、急速な民主主義改革が行われ、申告納税制度の採用、税務代理士制度の改正に関するシャウプ勧告等により、納税義務を適正に実現するには、職業専門家の援助を得ることが必要であるとの見地から、従来の税務代理士法に代えて、昭和26年6月15日新たに「税理士法」が制定されました。この税理士法には、税理士の職責、業務の範囲、税理士試験、事前通知制度などについて詳細な規定が設けられました。 |
| 『税理士法改正(第一次)』~任意加入制から強制入会制へ | |
| 昭和31年 (1956年) |
税理士業務を行おうとする者は、税理士登録を行い、かつ、税理士会に入会しなければ、原則として業務が行えないこととなりました。 |
| 『税理士法改正(第二次)』~登録事務を移譲 | |
| 昭和36年 (1961年) |
税理士会の自治権を強化するため、登録事務が国税庁から日本税理士会連合会へ移譲されました。 |
| 『税理士法改正(第三次)』~税理士の地位が明確に | |
| 昭和55年 (1980年) |
税理士業務のより適正な運営に資するため、税理士の使命の明確化、税理士業務の対象となる税目の拡大、登録即入会(税理士登録をした者は当然に税理士会の会員となる)などの改正が行われ、税理士の地位が明確になりました。 |
| 『税理士法改正(第四次)』~納税者利便の向上と信頼される税理士制度の確立 | |
| 平成13年 (2001年) |
最近の税理士を取り巻く環境を踏まえた改正として、税理士法人制度の創設、税理士が税務訴訟において弁護士とともに出頭・陳述できる補佐人制度の創設、税理士業務に対する報酬の最高限度額に関する規定の削除などが行われました。 |
| 『税理士法改正(第五次)』~公認会計士に係る資格付与の見直し | |
|
平成26年(2014年) |
公認会計士の税理士資格の取得について、国税審議会が指定する税法に関する研修の修了を要件とすることとされたほか、租税教育への取組の推進、税理士に係る懲戒処分の適正化などの改正が行われました。 |
| 『税理士法改正(第六次)』~業務環境や納税環境のデジタル化に対応 | |
|
令和4年 |
税理士の業務におけるICT化推進の明確化や事務所設置規定の見直しなど経済社会のデジタル化に対応するための改正のほか、税理士試験の受験資格の見直し、税理士法人の業務範囲の拡充、懲戒逃れをする税理士への対応などが行われました。 |
税理士記念日の由来
我が国の税理士制度は、昭和17年2月23日、税務代理士法によって初めて法制化されました。この日を税理士記念日と定め、毎年各地で税の無料相談や座談会等、各種の行事を行っています。現行の「税理士法」は昭和26年6月に制定され、その後10数回に及ぶ改正により、特に税理士会の強化充実と自主性の確立が図られ、現在に至っています。